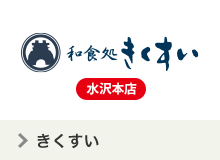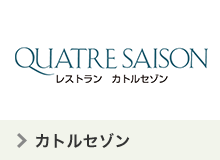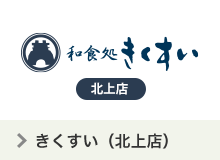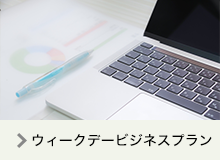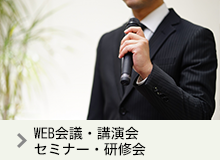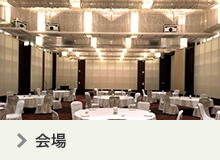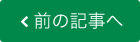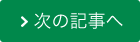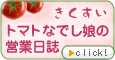トマト丼の取材(めんこいテレビ)

先日めんこいテレビからトマト使用した丼をテレビ放映したいとお話しがありわくわくドキドキの収録だった。白衣の裾にマイクをし、村上まゆこアナウンサーとオープンキッチンの前のカウンターで籠に盛った完熟トマトをバックにスタート。「佐藤料理長は大のトマト好きだそうですが」と好きになった訳を聞かれたが。俺も分からん、好きの物は好きみたいなお話しをした。何と1回でOK、え~これでいいの、でも一安心、次は村上まゆこアナウンサーがトマトレモン煮と、メインのトマト丼を食べている時は同じテーブルにて会話をして下さいとの事。うわ~俺の苦手な会話か、スポットライトを浴びると暑いし、そんなにお話をする訳ではないが口が渇いてくる。では本番行きます、ドキドキ、村上さんの言葉にハイ、そうですね、とうなずくのが一杯の収録でした。8月18日(土)6時半から、めんこいテレビの山海漬と言うテレビ番組で放映になります。是非見てください。私の顔が映っても物を投げないで下さい。